無料講座に参加した一人が、恥ずかしそうにノートを取り出した。
ノートを開く手は少し震えており、どこか恥ずかしそうにして目を伏せている。官公庁で働き、今後関連プログラムのマーケティング、広報業務も担当する予定らしく、いくつか考えたアイデアを他の人に初めて共有するのだという。伝えなければならない素材についての簡単な説明が続き、関連してターゲット世代に関する記事で見たインサイトと、自身の共感した部分、そして参考文献。いつの間にか、非常に馴染みのある場面が目の前に再び広がっていた。
そして、私の意見を待っている不安と期待の目と目が合うと、私は答えを決めなければならないことに気づいた。
-
顧客であったあるグローバルNGO団体で働いていた元国連気候政策専門家の方が、スウェーデンのあるエージェンシーが実施したクリエイティブワークショップに参加した自身の経験を共有してくれたことがあった。ワークショップのテーマは「あなたもクリエイティブになれる」だったという。
A3サイズの大きな画用紙に横線と縦線を引いて合計25個のマスを作り、チームメンバーが円卓に座って一人ずつ「リンゴ」に関するイメージを思い浮かべて埋めていく方式だった。果物「リンゴ」から始まり、MacBookの上部の様子まで、様々な「リンゴ」に関連するイメージが埋められていき、その成果物を見て皆で祝い、あなたもクリエイティブだと自信を持てという叫び声に高揚した経験についての話だった。
実は、私はこれらのアイデアの存在目的について疑問を投げかけざるを得ない。このように絞り出したアイデアが、本当に期待される役割を果たせるのだろうか?誰のために、どのような意味でアイデアが納得できるものなのかという疑問。

マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger)
ハイデガーが語る現象学的な視点から「人間は生まれたときからすでに世の中に投げ出された存在」である。そのような私たちが自身の存在に意味を与え、確認する方法とは「それぞれが属している世界とその中の他の存在をCaringしながら生きていくこと」と表現する。ここでのCaringは、世話をする、関心を寄せる程度に理解できる。私たちが一般的に金を稼ぐために語る事業、ビジネス、サービス、製品、売上、営業、マーケティングといった用語は、基本的にBuyingとSellingの役割を担う「人々に関する話」である。
アイデアそのものに意味はない。
そのアイデアが反映された成果物、製品、戦略、または広告コンテンツとして、最終的にエンドユーザーまたは消費者が自身の日常的な現実へ容易に当てはめることができるか否かで、その意味発生の可否が決まる。つまり、「人々の日常とどれほど意味のある形でつながっているのか、その意味が彼らにとっても本当に意味のあるものなのかという判断ができる情報がなければ、アイデアに対する評価と価値はそもそも確認不可能である。
アイデアはアイデアそれ自体としては、企画し、想像し、組み合わせることに面白さを感じることができる。しかし、このアイデアが世の中の誰かがCaringしていることとつながった意味を伝えたり、作り出したりするなど、人々の現実とつながっていなければ意味が生じず、この理解を通してアイデアの妥当性を判断できるようになる。
人間は存在の意味を見つけるために他者に興味を持つものであるというハイデガーの視点に、この記事を読んでいる皆さんが同意するのであれば、「アイデアもまた、私ではなく、私が知らない知らない世界に住んでいる、他者に興味を示し、それを通して彼らにとっても意味のある内容を伝えることが、アイデアの存在意義ともつながる」ことにも共感できるだろう。
-
消費者中心、User-centered戦略などの用語は馴染みがあるため、私には軽く見えてしまうこともある。人がまず存在し、彼らを消費者またはユーザーと呼ぶ企業の視点が加わっただけで、自然状態での人々の日常を見ることには、依然として限定的な意図があるのだ。
成功した事業家たちが自分自身に投げかける「自身の事業は社会にどのような影響を与えるのかという問いは、それゆえに、より根源的な、以降のあらゆるアイデアの存在理由において、本人と世の中を納得させる力がある。
p.s. もしアイデアが人なら、私は彼/彼女とのインタビューで、以下のような返答を聞くのではないかと想像する。
「人々は私がなぜ存在するのかに興味がないんです。どんな服を着せるか、どんな仕事をするかだけに興味があるだけ。」
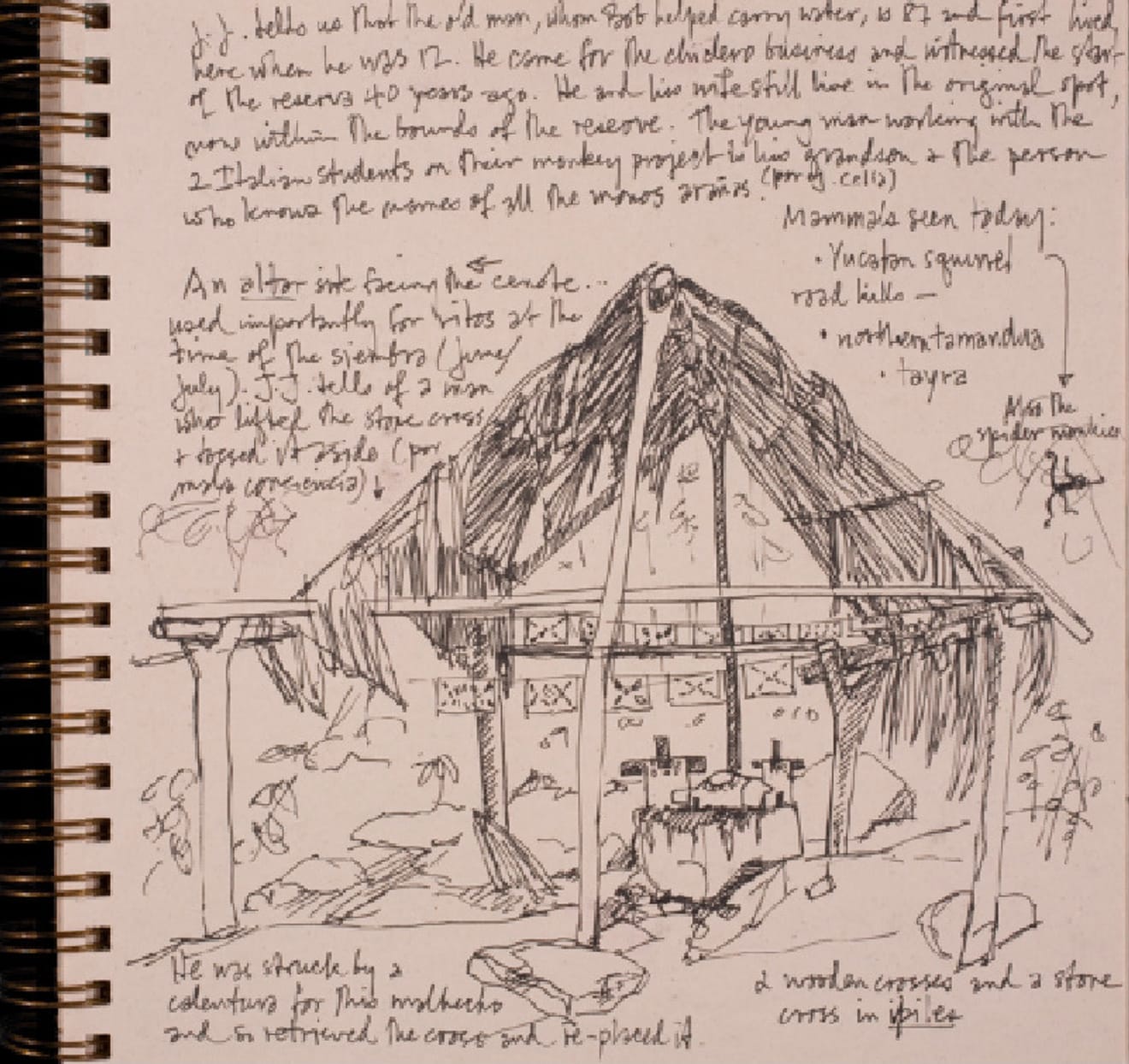
ビジュアル・フィールド・ノート:ユカタンでの洞察を描く(Visual Field Notes: Drawing Insights in the Yucatan)by CAROL HENDRICKSON
コメント0